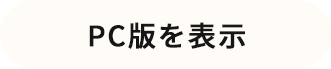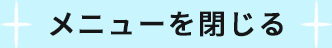梅嶺山法泉寺

ツツジと本堂
「梅嶺山法泉寺」:三戸町川守田字横道
臨済宗の寺院。本尊は釈迦如来。元和元年(1615)、藩主南部利直の長子兵六郎経直の菩提を弔うために開創されたと伝えられます。経直は庶子のため、家督を継がず福岡城主(岩手県二戸市)となり、十六歳で死去しました。
山門は三戸城の搦手門を拝領したものと伝えら、三戸城の名残を残す数少ない文化財となっています。
近年は敷地内のいたるところにツツジが植栽され、墓参り等に訪れる人びとの目を楽しませてくれます。法泉寺の住職は「ツツジのお寺として広く親しんでもらいたい」と話しています。ツツジのほかにも沙羅の木やエドヒガンザクラなども見ものです。

法泉寺山門
【法泉寺山門(旧三戸城搦手門)】 町指定文化財
法泉寺の山門は、三戸城の搦手門を28代南部重直より拝領したと伝えられています。
棟門形式で屋根は唐破風造りになっています。扉には八双金具や乳金具が備わっていて、棟の下には天井が張られています。

地獄図
【地獄図】江戸時代
中央上部に閻魔王が座し、右に司録、左に司命、閻魔王の下には罪人の嘘を調べる見目(みるめ)と嗅鼻(かぐはな)がいます。
右上には手招きする女性を目指し針山を登る亡者、左上には血の池に落ちる亡者がいます。
下半分の右から地獄から亡者を救い出す地蔵菩薩、釜茹でされる亡者、馬頭に舌を抜かれる亡者、浄玻璃の鏡に映される亡者とそれを見せる牛頭、臼と杵でつかれ捏ねられる亡者たちが描かれています。

達磨大師座像
【達磨大師座像】 江戸時代
5世紀頃の人で禅宗の開祖とされています。南天竺(インド)の王国の第三王子として生まれ、仏教の僧侶として中国で活躍しました。達磨が面壁九年の座禅によって手足が腐ってしまったという伝説が起こり、現在の「だるま」が誕生しました。

【比丘尼座像】 江戸時代
釈迦の弟子として出家した男性は「比丘」、女性は「比丘尼」と呼ばれました。像の頭部には剃髪(髪をそること)の跡が表現されています。

【沙羅の木】
ナツツバキ、沙羅双樹とも呼ばれる落葉広葉樹。6月~7月にツバキに似た白色の花をつけます。平家物語の冒頭の一節でもおなじみ。

【エドヒガンザクラ】
数多い桜の中でもエドヒガン群に属する種類。彼岸の頃に開花し、関東を中心に広く分布していることから、エドヒガンザクラと呼ばれています。盛岡市の石割桜や小岩井の一本桜などで知られます。
広報さんのへ2009年6月号(No.574) 三戸町の古寺 より
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1157 ファクス:0179-20-1114
更新日:2019年12月10日